道路交通法の改正により、今年から日本でレベル3の自動運転が解禁されます。
2010年代前半から自動車メーカー各社が力を注いできた自動運転車が、いよいよ公道に姿を現し始めることになります。
自動運転技術の実用化による変化は、単に車を運転しなくても良くなる、ということだけではありません。
今まで人間が車を運転することを前提に構築されてきた社会が、運転の自動化によって大きく姿を変えることになると予想されています。
今回は、近未来技術の中でも特に重要な”自動運転”の現状と未来についてご紹介します。
自動運転のレベル

自動運転とはその名の通り、運転を自動で行うシステムのことですが、
どれだけシステム側が運転を主体的に行うかによって、0~5までのレベルが定義されています。
- レベル0・・・手動運転
- レベル1・・・運転補助
- レベル2・・・一部自動運転
- レベル3・・・条件付自動運転
- レベル4・・・高度自動運転
- レベル5・・・完全自動運転
レベル0 手動運転
ハンドル、アクセル、ブレーキの全てをドライバーが操作します。
つまり自動運転機能がついていない全ての自動車がレベル0に該当します。
今路上を走っている車の多くがレベル0で、これが本来の自動車といったところでしょうか。
レベル1 運転補助
ハンドル操作、加減速のいずれかをシステム側が操作します。
例えば高速道路でのレーンキープ機能や前車に一定間隔で追従することができるクルーズコントロールなどが該当します。
あくまで運転補助なので、レベル0と同様常に前方を注視し、システムが介入していない運転操作については
ドライバーが行う必要があります。
レベル2 一部自動運転
ハンドル操作、加減速の両方をシステム側が操作します。
高速道路など限定された環境で使用が可能で、ほとんどの自動車メーカーが既に実用化している機能です。
基本的にはシステム側が全て操作してくれますが、ハンズフリー(手離し)はできない場合が多く、ドライバーは常に前方を注視しハンドルに手を添えておくことが要求されます。
レベル3 条件付自動運転
レベル3以上は運転の主体がシステム側になり、一定条件内で全ての運転操作をシステムが行います。
ただし、緊急時などで自動運転を継続できなくなり、システムの要求があった場合はドライバーが運転を引き継ぎます。
そのため、いつでも運転できるような状態でいる必要があります。
日本では2019年に道路交通法改正でレベル3の自動運転車を販売許可することが決定しました。
2020年に、まずはホンダが”高速道路での渋滞時”に限定した自動運転機能を持つ自動車を販売する予定で、
その後各メーカーが一般道にも対応した機能を展開していくと思われます。
レベル4 高度自動運転
レベル4では”限定領域内”において緊急時も含め人間が一切運転操作を行うことなく走行することができます。
Googleから分社したWaymoでは既にレベル4相当の”無人タクシー”が運用されており、日本でもレベル4ではエリア内で無人走行が認められるようになるのではないかと思われます。
将来的には都市部でのタクシーや拠点から拠点への輸送手段として使用されることになるでしょう。
ただし、”限定領域外”で走行する場合に備えて手動運転もできるようにハンドルなどは残される可能性があります。
レベル5 完全自動運転
あらゆる条件、場所で人間が一切運転操作を行うことなく走行することができます。
手動運転に必要な装置は一切不要になるので、車内をオフィスとして活用したり、目的地に到着するまで睡眠をとるなど自由に過ごすことができるようになります。
まさに移動する部屋といったところでしょうか。
ただし、現時点ではまだ実現性に課題が多く残っており、人間と同等以上の判断力と正確性を備えたAIを搭載することが必須となりそうです。
実用化はどこまで進んでいるのか?
自動運転の実用化のために、自動車メーカーはもちろんのこと、GoogleやNVIDIAなどのIT企業もこの分野に力を注いできました。
現在は日本を含む世界中で路上試験が盛んに行われていますが、現時点で実用化はどこまで進んでいるのでしょうか?
一般販売されている自動車
近年販売されている自動車では、レベル2相当の自動運転機能が多く搭載されるようになっています。
日本車では日産”プロパイロット”などがこれに該当し、2019年にはハンズフリー(手離し)で追い越しを行う機能も登場し始めています。
海外ではテスラ社の”オートパイロット”が特に先進的で、まだ完全な手離し運転はできませんが、自動運転に必要なハードウェアは整ってきており、 将来的には ソフトウェアのアップデートにより完全自動運転ができるようになる予定です。
自動運転実験車
2020年現在、最も高度な自動運転実験を行っているのはGoogle社から分社化したアメリカのWaymoで、 2019年からカリフォルニア州で自動運転無人タクシーの試験運用を開始しています。
日本でも大学、タクシー会社などが路上試験を重ねており、東京オリンピックまでには一定区間内で自動運転タクシーが利用できるようになるとされています。
自動運転が社会に与える影響
レベル5のような完全自動運転車が実用化されると、社会にどのような影響を与えるのでしょうか?
自動車が発明されてから100年以上が経ちますが、今までの自動車は人間が運転することを前提として設計され、そして道路のようなインフラもそれに合わせて設計、構築されてきました。
その運転という作業が、今初めて自動化できるようになろうとしています。
自動運転が社会に与える影響について、プラス面とマイナス面の一例を見ていきましょう。
旅行や通勤が楽になる
運転が好きな人にとっては、自動車での旅行はもちろん通勤ですら楽しみの一つですよね。
でも、旅行中の高速道路での渋滞や、仕事で疲れているとき運転は苦痛に感じてしまうこともあります。
自動運転が実用化されれば、そんな苦痛からも解放されます。
もちろん常に周囲の状況を把握しておかなければならないことは変わりませんが、今までよりも景色や同乗者との会話を楽しんだり、ちょっとした仕事を車内で済ませるといったことも可能になるでしょう。
車を持つ必要性が薄れる
日本で車を所有する場合、各種税金や維持費によってかなりの経済的負担となってしまいます。
レベル4以上の自動運転が実用化し、無人で走行可能になれば車を所有する必要性が薄れる可能性があります。
毎日車を運転する人であっても、自家用車は走っているより駐車場に停められている時間の方がはるかに長いものです。
その時間を無駄にすることなく、車を複数人でシェアして常に路上を走らせながら待機させておけば、利用者がいつでも呼び出すことができるので、行きたいときに行きたい場所へ自由に移動できるようになります。
通常のタクシーと比べて料金も安くできるでしょうから、車を持たなくても十分生活できるようになるでしょう。
交通事故が減る

日本での交通事故による死亡者は年々減り続けており、これは大変すばらしいことです。
その理由としてドライバーの安全意識の高まり、自動車の安全性能向上、医療技術の進歩などが考えられます。
しかし、それでもまだ2019年時点で年間3000人以上の命が交通事故によって失われているのです。
そして交通事故の90%以上は、人間の判断ミスや操作ミスといった”ヒューマンエラー”によって引き起こされています。
過去に自動運転の実験中、歩行者に衝突して死亡させるなど悲しい事故は発生していますが、事故の発生件数と自動運転車の走行時間を比較すると、自動運転車の事故率は人間が運転する場合よりもはるかに低いようです。
自動運転システムは疲労せず、人間のように感情に左右されることがないからでしょう。
反応速度や運転操作の正確性もすでに一般のドライバーを上回っていると言われています。
自動運転者の割合が増えれば、ヒューマンエラーがなくなるので交通事故件数もその分減少していくと考えられます。
また、当分先のことにはなるでしょうが、もしほぼ全ての車が自動運転車になれば、現在路上を埋め尽くしている道路標識や看板も不要になるので、街の景観もかなり良くなるのではないでしょうか。
運転を仕事にしている職業が縮小・低賃金化する
完全自動運転が実用化し、それが広く普及した場合とても便利な社会を実現できるでしょう。
しかし、いつの時代でも大きな変化やイノベーションはメリットばかりを与えるわけではありません。
現代では、タクシー運転手やトラック運転手など、運転を仕事にする職業が多くあり、そしてそれを生業としている労働者の数は決して少なくはありません。
もし無人での自動運転車が実現し、普及した場合はそれらの仕事に就く人の生活が脅かされることになります。
”機械に接客や荷物の積み下ろしができるはずがない”、と考える方もいるでしょう。
しかし、AIやロボティクスの技術は驚くべきスピードで進化しています。
今無理だからと言って、10年先も無理だとは言えないのです。
とはいえ、やはり人間に運転してもらいたいという人もいるので、ドライバーという仕事が完全になくなる可能性は低いですが、それでもその仕事に就く人の需要減少による賃金低下が起きる可能性は十分に考えられます。
人間にしかできないサービスにより付加価値を与え、自動運転との差別化を図ることが重要になるでしょう。
運転する楽しみがなくなる?
もし自動運転が人間が運転する場合よりもはるかに安全であると証明された場合、将来”手動運転のみ”の自動車の販売が禁止される可能性はあります。
これは決してあり得ない話ではありません。
例えば、ヨーロッパ各国では将来的にEV(電気自動車)へシフトすることを目標に掲げており、イギリスでは当初の予定から4年前倒しで、2035年までにガソリン、ディーゼルなど内燃機関で動く自動車の販売を禁止することを決定しました。
国の主導によって技術の転換を迫られることは現実に起こりうるのです。
もしそうなった場合、車の運転を楽しみにしていて、自動運転機能は必要ないと思っている人にとって車はとても退屈なものになってしまうでしょう。
”サーキットで走ればいいじゃないか”という意見もありそうですが、街や自然の中を自分の運転で走りたいという人も多く存在するのです。
オートマチック車が進化した現在でもマニュアル車が販売され続けているように、せめて手動運転と自動運転を切り替えられる車種は残してほしいものですね。
自動運転が抱える問題
事故の責任は誰がとるのか?
自動運転車が何らかの原因で事故を起こしたり、事故に遭った場合の責任を誰が負うのかが問題になります。
自動車メーカーが責任を負う場合、自動運転車を発売すること自体メーカーにとって大きなリスクになりますし、搭乗者が責任を負う場合は「自分が事故を起こしたわけではないのに!」と理不尽に思ってしまうでしょう。
今後の法整備では、事故の責任はレベル3までドライバー、レベル4以上は自動車メーカーが負うという形になるようです。
それでも、運悪く死亡事故になってしまった場合、遺族は自動車メーカーと搭乗者のどちらも100%責めることができず、やり場のない怒りを抱えることになってしまいそうです。
責任の所在明確化は避けて通れない問題です。
ハッキングされる可能性
近年発売される車は何らかの形でインターネットに接続することが可能であり、既にテスラ車などソフトウェアアップデートをインターネットで行っている自動車もあります。
しかし、インターネットとの親和性が高いデバイスであるということは、悪意のあるハッカーがいればハッキングすることも可能になるということ。
現に自動車をネットワーク経由で乗っ取り、操作することが可能であることが実験によって証明されており、もし自動運転車が普及した後にそのような事態になれば、無人の自動車を兵器として使用したり、様々な犯罪に悪用することができるようになってしまいます。
完全自動運転車の実用化には、絶対に乗っ取られない強固なネットワークセキュリティを構築することが必須であると言えます。
運転免許の必要性
人間が運転に関与しないレベル4以上の自動運転車が走る場合、運転免許を持った人が搭乗する必要があるのか?といった問題も議論されています。
やはり人間が運転しない以上、運転技能は必要なく単なるオペレーターとして乗車すればよいのでしょうか。
先に紹介したWaymoが運用している自動運転タクシーの試験運用では、すでに運転席にドライバーが座っていないため、日本でもレベル4以上は無人運転&免許不要になる可能性が高いです。
自家用車の場合は今後慎重に議論していく必要があります。
しかし、運転免許不要となれば自動車に興味を持つ人も減るでしょうし、現在少子化による免許取得者減少によって厳しい経営を強いられている自動車教習所などは、さらに厳しい状況に追い込まれることになりそうです。
まとめ
自動運転の現状と未来についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
ひと昔前まではSFの中のテクノロジーだった自動運転ですが、私たちの前に現れる日は着実に近付いてきています。
車の運転が好きな人も嫌いな人も、どちらも納得できるような形で実現してほしいですね。
当分の間は手動運転が主流になりそうなので、ドライバーの方は交通ルールと運転マナー遵守し、歩行者の方も車に十分気をつけるようにしましょう。


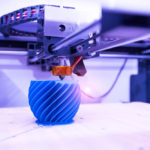




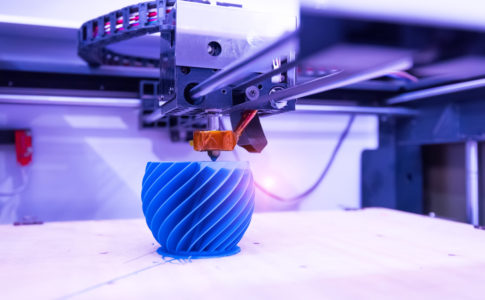





コメントを残す