こんにちは!
あいかわらず新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっており、感染者数、死者数が留まることを知らずに増加し続けています。
残念ながら東京オリンピックも来年以降に持ち込みとなりそうです。
一日も早く収束へ向かうことを祈るばかりですね。
さて、今回は私たちの食や健康にも今後影響を与える”ゲノム編集”というテクノロジーについてご紹介したいと思います。
ゲノム編集とは何か?
地球上に存在する生物は動物、植物に関わらずその全てがDNA(遺伝子)を持っていることは皆さんご存知のことだと思います。
生物の体や性質はそのDNAを元に構築されるので、DNAはいわば生物にとっての設計図であると言えます。
ゲノムはこのDNAが持つ情報の総称のことを指します。
ゲノム編集とは、簡単に言うとDNAの中のねらった部分だけを、まるで映像を編集するかのように自由に書き換える技術のことです。
つまり、生物の形や性質を自由に編集できる”命を操作する技術”と行っても過言ではありません。
その中でも、2010年代に発表されたCRISPR-Cas9(クリスパーキャス9)という革新的手法が特に有名です。
遺伝子を組み換える方法の種類
生物の遺伝子を組み換える方法は昔から存在していましたが、ゲノム編集は従来の方法と何が違うのでしょうか?
品種改良
人類が行ってきた遺伝子組み換えの最も古い手法として、品種改良があります。
例えば、現在様々な種類が存在する家畜や一部の野菜などは、人間にとって有用な特性を持つことを期待して、交配を重ねて生み出されたものです。
DNAを直接操作するわけではありませんが、品種改良もある意味遺伝子組み換え技術の一部と言えるかもしれません。
しかし、品種改良ではねらった通りの特性を持った品種が誕生する確立は低く、世代を重ねる必要があるため何十年、さらには何百年と言った時間が必要になることもあります。
遺伝子組み換え技術
遺伝子工学の発達でDNAと言う存在が発見されてから、そのDNAを直接組み換える研究が進められ、20世紀後半に誕生した技術が遺伝子組み換えです。
遺伝子組み換えは、化学物質の”変異原”を使用してDNAのある場所に別の遺伝子を組み込んだり、あるDNAを働かなくさせたりすることが可能で、開発当初は画期的な技術でした。
しかし、思い通りにねらったDNAだけを組み替えることは非常に難しく、何千回も実験を繰り返して偶然成功するのを待つという、運に頼った一面もありました。
そのため品種改良ほどではないにしても、長い作業期間が必要になるのです。
ゲノム編集の誕生
そして2000年代に技術革新で誕生したのが”ゲノム編集”です。
ゲノム編集は従来の遺伝子組み換えと比べて以下のような特徴があります。
- 基礎的な遺伝子工学の知識があれば簡単に編集できる
- ねらい通りに編集できる確率が高い
- 様々な生物に適用できる
DNAは4つの塩基(アデニン、シトシン、チミン、グアニン)で構成される二重らせん構造体です。
ゲノム編集はねらった塩基と結合する性質がある物質を、まるでDNAを切り取るはさみのように使用することで成功率を高めています。
従来の遺伝子組み換え技術に比べると、大幅に時間を短縮できる圧倒的に効率の良い方法なのです。
ゲノム編集の活用方法
生物の形や性質を自由に変更できるゲノム編集ですが、いったいどのようなことに使われようとしているのでしょうか?
品種改良
現在私たちが食料にしている肉、魚、野菜などの中には、品種改良によって生み出されたものもありますが、まだまだ自然の姿のまま栽培、養殖したり、採集しているものが多くあります。
ゲノム編集の技術を利用すれば、養殖する魚を早く大きく育つようにDNAを操作したり、実をたくさん実らせ病気にも強い野菜を生み出すといったことも可能になります。
2019年には厚生労働省がゲノム編集を使用した食品に対し、届出を行えば販売を許可することを決定しました。
それだけゲノム編集が確実な技術であるということなのでしょう。
やせた土地でも早く大きく育つ野菜を作り出すことが出来れば、現在も飢餓に苦しむ貧しい国の人々を救うこともできるかもしれません。

医療
ゲノム編集には様々な生物に適用できると言う特徴がありますが、その中にはもちろん人間も含まれます。
現在、世界中でゲノム編集をはじめとした遺伝子操作技術を難病の治療などに活用しようと言う試みが活発に行われており、すでに治験も始まっています。
例えば、筋ジストロフィーという全身の筋肉が徐々に失われていく病気がありますが、この病気はDNAの変異によって発症することが知られています。
日本では東京大学や大阪大学などの研究チームが、筋ジストロフィーの患者から作成したiPS細胞で、患者の組織を再現し、ゲノム編集を行ってDNAを修復することに成功しました。
また、海外でも癌やHIVといったさらに患者数が多い病気に対して活用方法が研究され、それぞれ成果を挙げています。
ゲノム編集は再生医療と並んで医学界の画期的なイノベーションであり、2020年代には病気に苦しむ多くの人に希望を与えることになるでしょう。
ゲノム編集の問題点
生物の性質を人工的に変えるということは当然リスクも伴います。
ゲノム編集によってもたらされる可能性がある問題点についてその一部をご紹介します。
自然界に存在しない生物をつくるリスク
ある生物の遺伝子を改変したり、他の生物の遺伝子を取り入れたりすることは、本来自然界に存在しない生物を作るということです。
ゲノム編集でその生物が人間にとって役に立つ特性を持つことが出来たとしても、思わぬところで生態系に悪影響を与える可能性はゼロではありません。
ゲノム編集は遺伝子工学の知識と設備があればある程度簡単に行えることがメリットですが、様々なリスクが伴うことを良く知り、十分な検証を行った上で活用するべきでしょう。
デザイナーベイビー
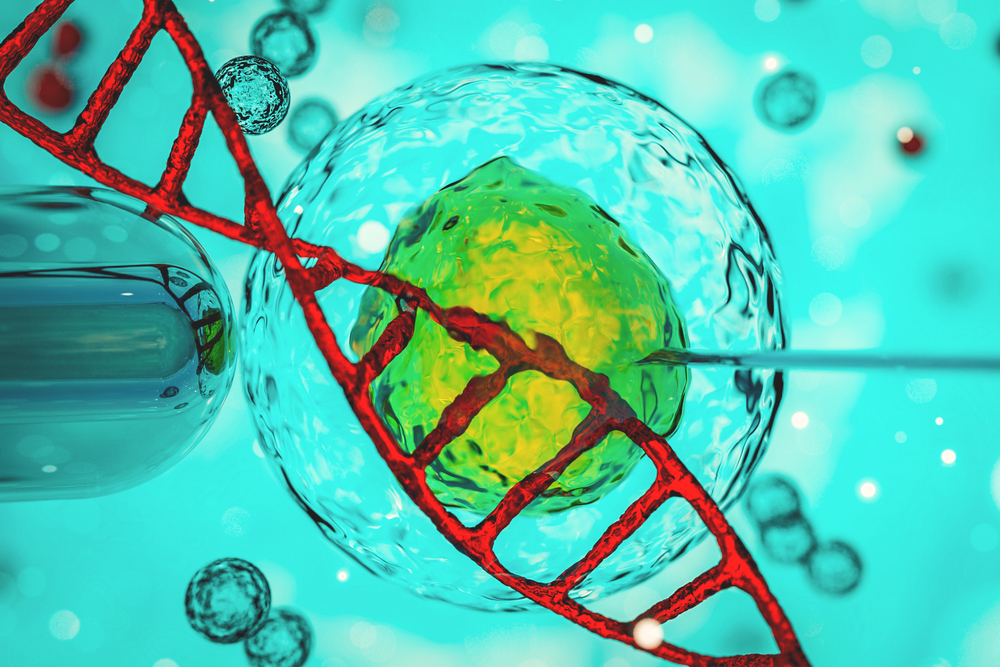
2018年11月、中国から衝撃的なニュースが届けられました。
受精卵の段階でゲノム編集を施された、双子の赤ちゃんが誕生したというのです。
この双子の赤ちゃんは、HIVウイルスに生まれつき感染しないようにDNAが操作されたということでした。
ゲノム編集を行ったのは大学教授で、この教授は中国内外から多くの批判を受けました。
遺伝子操作を受けて生まれた赤ちゃんを”デザイナーベイビー”と呼びますが、デザイナーベイビーは安全面、倫理的な課題が多く残っており、それらをクリアする前に行ってしまうことは重大なタブーです。
ゲノム編集を生まれる前の人間に対し行うことは、たとえ病気にならないようにするためであったとしても、十分すぎるほどの検証が必要なのです。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回の内容をまとめると、
ゲノム編集は、生物のDNAを映像を編集するかのように書き換えられるテクノロジーで、
- 基礎的な遺伝子工学の知識があれば簡単に編集できる
- ねらい通りに編集できる確率が高い
- 様々な生物に適用できる
と言う特徴がある。
品種改良や医療での実用化が始まっているが、自然界に存在しない生物を作ることで生態系に悪影響を与えたり、デザイナーベイビーを生み出してしまうリスクがある。
画期的がテクノロジーであるからこそ、人類に与える影響が大きいことを忘れないようにしたいですね!



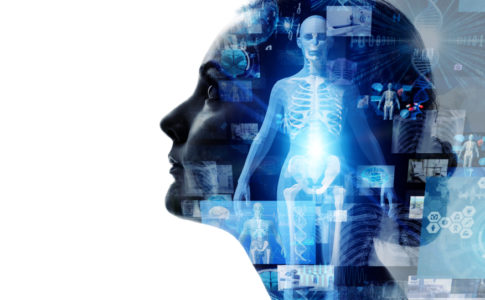



コメントを残す